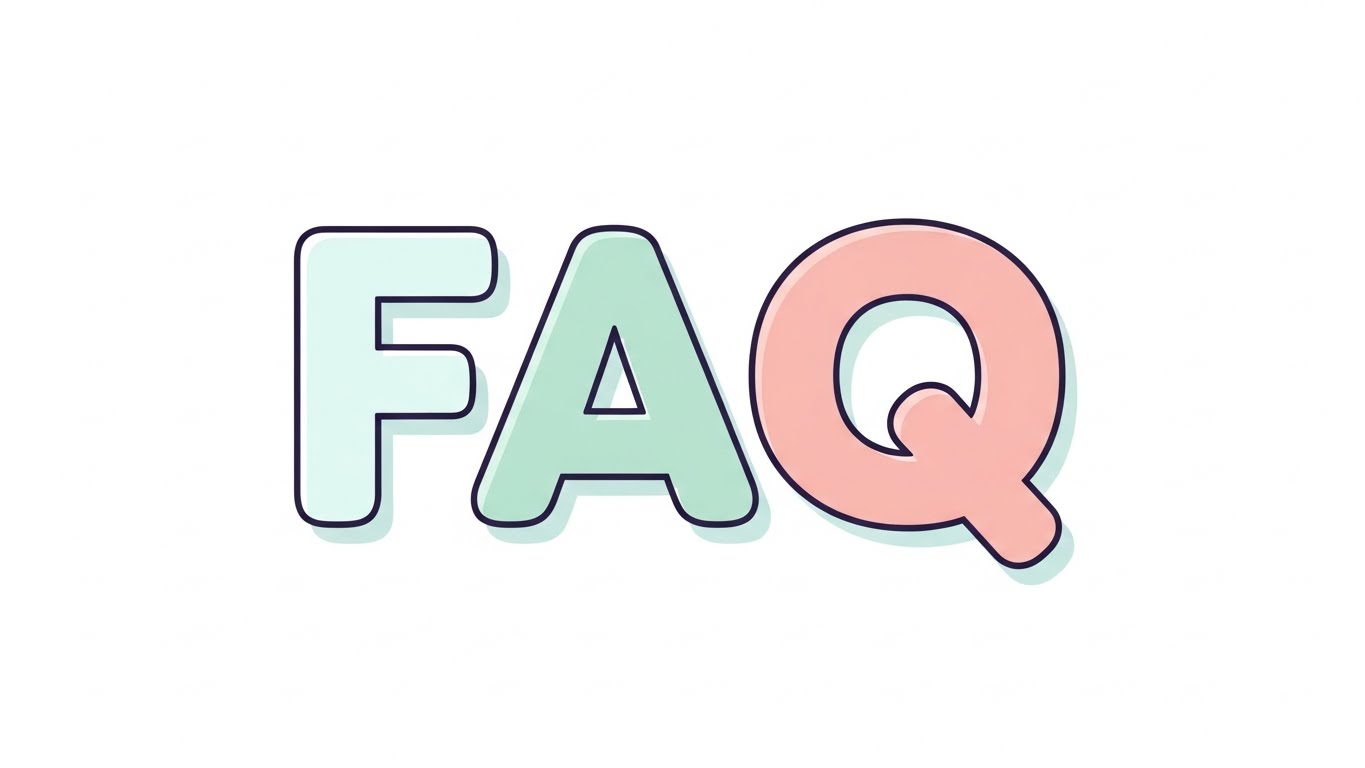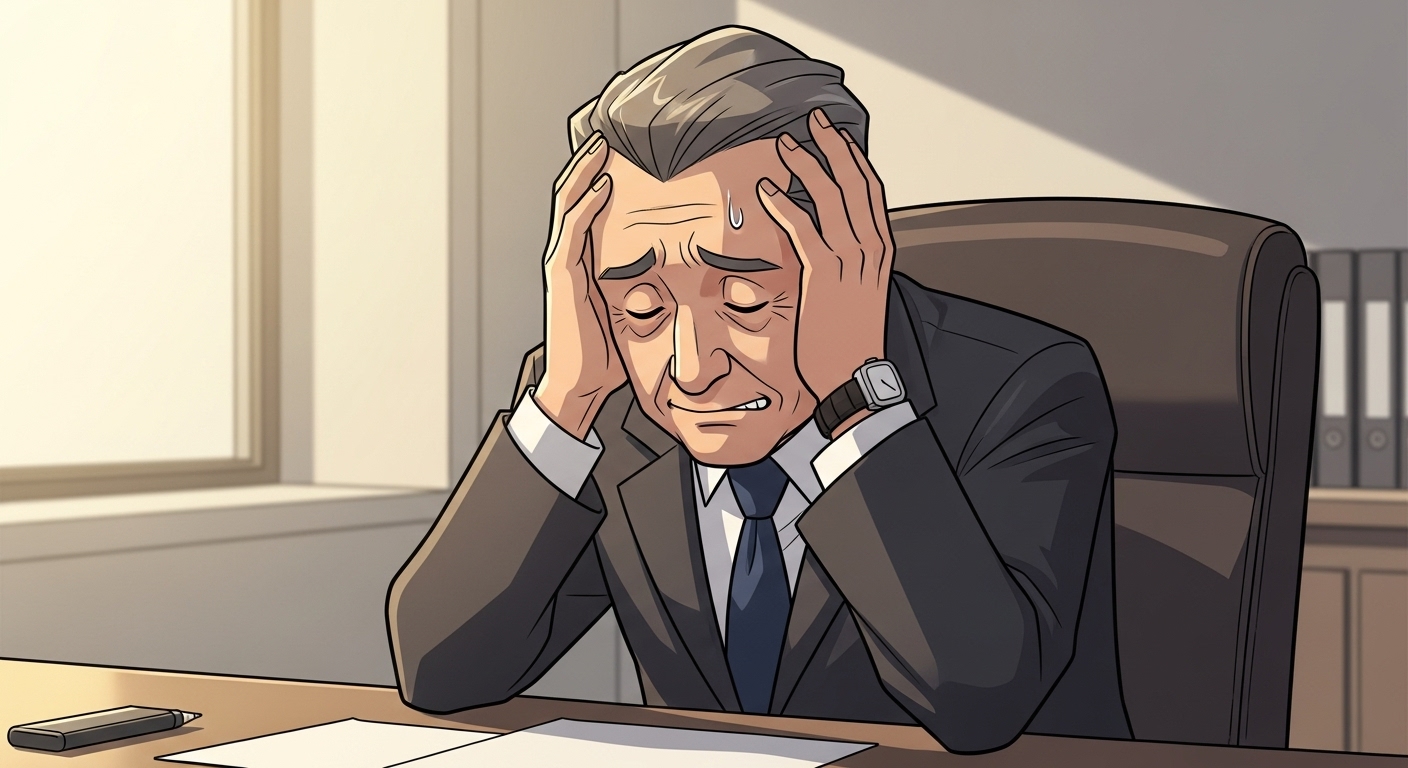料金当ステーションにご依頼を頂いた場合の各種料金のご案内です。宅建業免許申請代行許可区分法定費用(※1)報酬(税込み)新規申請(+保証協会加入代行)33,000円88,000円更新申請33,000円77,000円変更届500円※免許証の書換が必要な変更の場合33,000円新規申請(大臣)90,000円165,000円更新申請(大臣)33,000円110,000円変更届(大臣)ー44,000円※上記金額は予告なく変更する場合がございます。(※1 法定費用)ご自身で申請されても必要になる費用です。法人の場合、役員2名から1名につき2,200円(税込み)を申し受けます。大阪府以外への申請の場合、事前にお見積りさせて頂きます。変更届で従たる事務所新設・移設の場合は、別途お見積りさせて頂きます。上記の他、供託金・分担金および保証協会への入会金等が別途必要です。宅建士登録・変更等代行項目法定費用(※1)報酬(税込み)宅建士登録申請37,000円8,800円宅建士変更登録-8,800円宅建士証交付申請-8,800円宅建士登録移転8,000円11,000円※上記金額は予告なく変更する場合がございます。(※1 法定費用)ご自身で申請されても必要な費用です。不動産会社設立パック項目報酬等株式会社設立88,000円(税込み)登録免許税(実費)150,000円定款認証費用(実費)52,000円宅建業免許申請代行77,000円(税込み)法定費用33,000円合計400,000円※上記金額は予告なく変更する場合がございます。登記は提携の司法書士が行います。(司法書士への報酬は上記料金に含まれています)法人の場合、役員2名から1名につき2,200円(税込み)を申し受けます。会社印鑑の作成費用等が別途必要です。当ステーションは「電子定款対応」です。会社設立時の印紙代4万円が不要です。
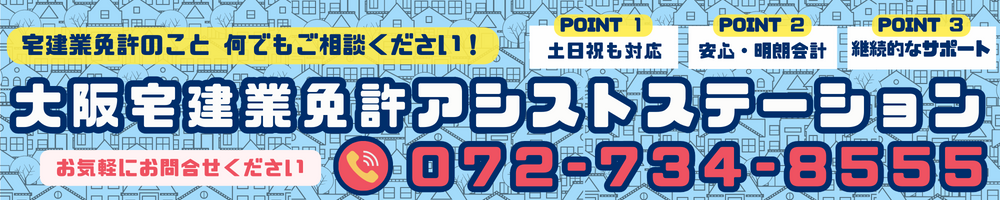




3.png)