宅建業免許の免許要件の一つに欠格要件に該当していないことがあります。申請者個人本人、法定代理人、法人の役員、政令の使用人等が規定の欠格要件に該当していない事が必要です。
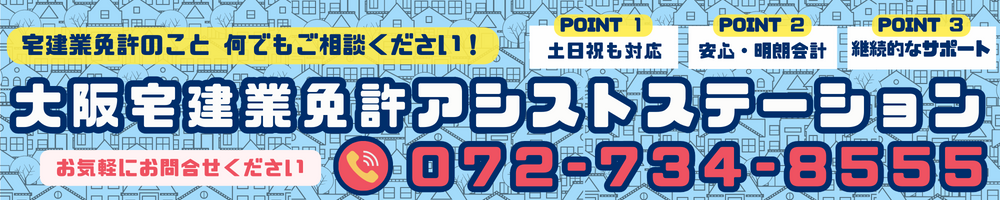
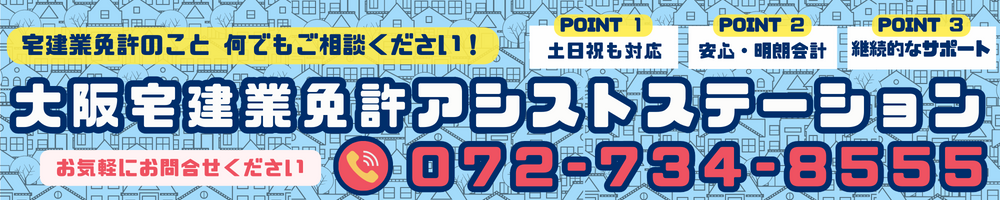
数量限定!自分で宅建業免許を取得するための「コツ」が分かる無料レポートプレゼント中
.png)
宅建業免許の要件の一つが「事務所」です。宅建業免許における「事務所」は重要な意味を持ちます。
事務所の所在(1つの都道府県だけにあるか、2つ以上の都道府県にあるか)によって免許権者(知事、大臣)が決まります。
また、事務所毎に「専任の宅地建物取引士」が必要であり、事務所の数に応じて「営業保証金を供託(又は弁済業務保証金分担金を保証協会へ納める)」しなければなりません。
「事務所」は特に重要な要件のため厳格に審査されます。
(添付書類の事務所写真等について細かくチェックされる事になります。)
事務所の範囲としては以下の通りです。
本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を行っていれば、本店も「事務所」扱いとなります。この場合、本店にも支店にも、営業保証金の供託(または弁済業務保証金分担金の納付)および専任の宅地建物取引士の設置が必要となります。
(本店で宅建業を行わなくても、支店で行う宅建業について、何らかの中枢管理的な統括機能を本店が果たしていると考えられるからです。)
支店については、従たる事務所の名称を「○○支店」として免許申請する場合は、商業登記が必要となります。商業登記がない場合は「○○営業所、○○店」等を用いて申請する必要があります。
事務所の適格性として「物理的」にも「社会通念上」も、「独立した業務を行いうる機能を持つ事務所として認識できる程度の形態」を備えていることが必要です。
これら適格性については、写真、平面図、契約書等で確認されます。
自分で宅建業免許を取得するための無料レポートプレゼント中